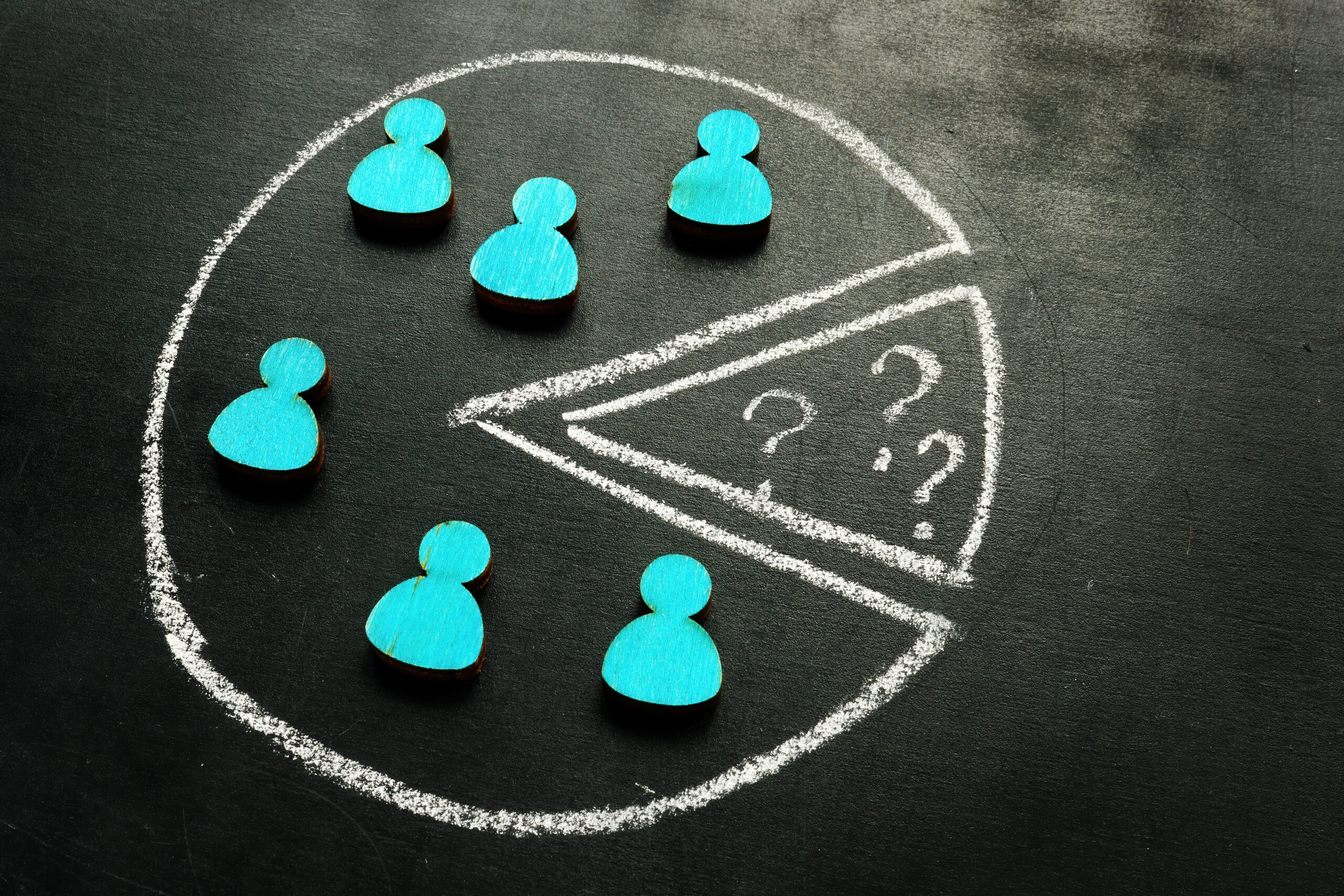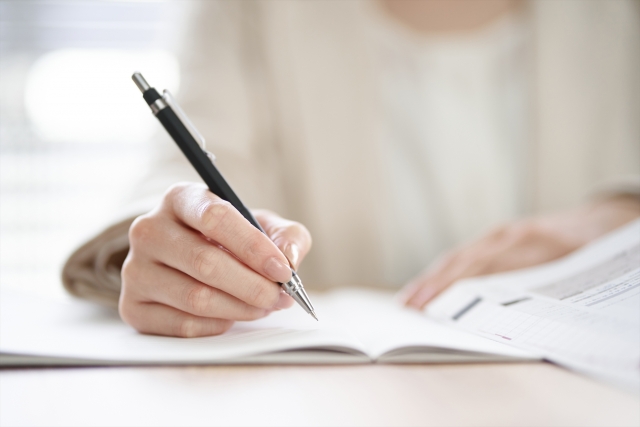相続は、時に予期せぬ形で私たちの人生に訪れるものです。故人が遺された財産は、その方の想いが込められた大切なものであり、どのように活用するかは、相続される方にとって重要な課題となることも少なくありません。
多くの場合、相続財産は、受け継がれた方々の生活を支えたり、将来への備えとして活用されます。しかし、中には、「故人の想いをより良い形で引き継ぎたい」「使い道に悩んでしまう」といったお気持ちを抱かれる方もいらっしゃいます。
今回ご紹介するのは、故人に寄付の遺志はなかったものの、相続財産を「寄付」という形で活用された方々の事例です。それぞれの背景や想いは異なりますが、故人の財産を社会貢献に繋げたいという共通の想いが見られます。以下に、具体的な3つの事例を見ていきましょう。
事例1:遺産分割後の余剰金をNPO法人支援へ
相談者: 相続人の配偶者
相続人: 複数
複数の相続人が遺産分割協議を行ったものの、分けきれないお金が数十万円残ってしまったケース。「このお金をどうしようか?」と悩まれた結果、寄付という選択肢を選ばれました。相続人の方々に寄付の意思はなかったとのことですが、相続人の奥様が代理としてご相談に来られ、故人の想いを受け継ぐ形で寄付をお受けいたしました。現金は1円単位で分けることも可能ですが、NPO法人への支援という形で社会貢献に繋げさせていただきました。
事例2:香典を故人の想いを繋ぐ寄付へ
相談者: 相続人
相続人: 1人
相続人の奥様が50代でご病気で亡くなられた事例です。お葬式では香典をご辞退されていたそうですが、それでも香典を持って来られる方がいらっしゃいました。故人を偲んで来てくださった方々の香典を、ご自身の財布に入れることに抵抗を感じられたそうです。そこで、「何か形で返したい」と悩まれた末、寄付を決断されました。寄付後、香典をいただいた方々におはがきで寄付された旨を連絡され、気持ちの整理をつけられたとのことです。
事例3:相続財産を社会課題解決のために
相談者:被相続人
相続人: 複数
ご兄弟が亡くなられ、まとまった額の遺産相続を受けたものの、相続人であるご自身は既に80代半ばというケースです。日々の生活に困ることはなく、贅沢な食事や旅行も難しい状況で、お金の使い道に悩まれていました。相続人の方は、かねてより社会問題に関心をお持ちで、高齢者の貧困問題やコロナ禍での社会的孤立、能登の地震からの復興の遅れといった現状を憂いておられました。そこで、遺産をNPO法人へ寄付することで、社会課題の解決に役立ててもらうことを決断されました。亡くなられたご兄弟は社会課題に特に関心はなかったとのことですが、相続人の意思を尊重し、寄付という形で遺産を活かしていただきました。
参考リンク