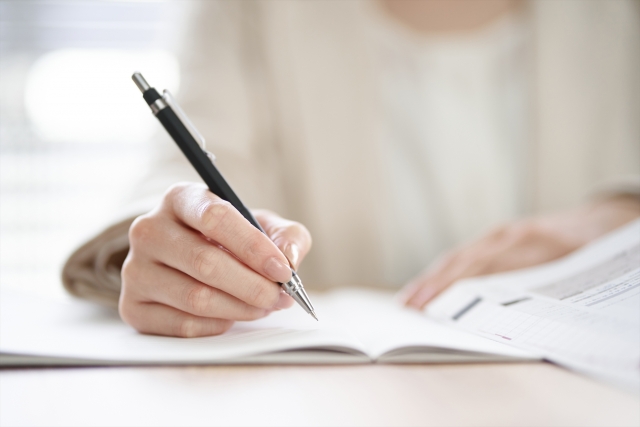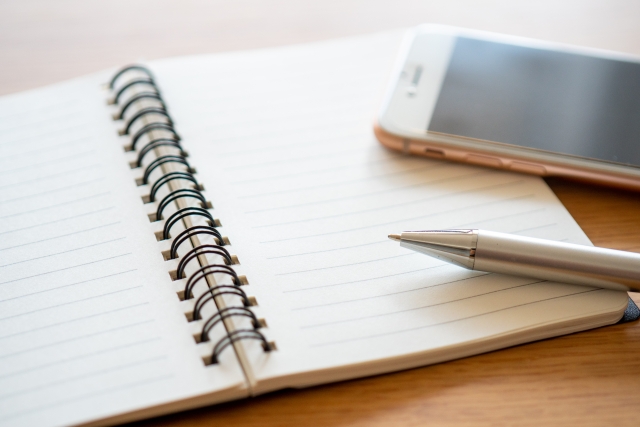「いつか社会のために役立ちたい」と、遺贈寄付をご検討される方が増えています。しかし、大切な財産を託すにあたり、々な不安を感じられるのは当然のことです。本稿では、遺贈寄付を検討中の寄付者が抱きがちな2つの不安と、その不安を解消するための2つの制度と1つの工夫について解説します。
遺贈寄付に関する2つの主な不安
遺贈寄付は、寄付者ご自身が寄付の結果を直接確認できないため、生前に以下のような不安を感じられるケースが少なくありません。
- 寄付先の永続性:
- 遺贈の実行には時間を要する場合があります。「10年後、あるいはそれ以降も寄付先団体が存続しているのだろうか」という不安です。
- 寄付金の使途:
- 「寄付金が意図した用途に確実に使われるのか」「約束は守られるのか」といった、寄付金の使途に対する不安です。
不安を解消するための2つの制度
これらの不安を解消するために、以下の制度が設けられています。
寄付先団体の永続性について
法人の種類によって、解散時の財産の扱いが異なりますが、NPO法人や公益法人は、清算時に類似の活動を行う団体や行政に事業を引き継ぐ義務があります。
参考資料:公益法人の解散に伴う手続について(https://www.koeki-info.go.jp/content/kouekihoujinkaisan.pdf)出典:内閣府 公益法人インフォメーション
また、寄付金の使途が指定されている場合、その指定に沿った使途以外は認められません。
例:「1,000万円を10年にわたって分配する」という条件で寄付した場合、10年かけて計画的に取り崩す必要があります。資金が余ったとしても、運営費への流用はできません。
このように、遺贈先団体が解散する可能性はゼロではありませんが、公益法人であれば、寄付者の意に反した使途を防ぐ制度設計がなされているため、ご安心いただけます。
寄付金の使途について
「寄付金が本当に意図した形で使われるのだろうか」という不安は、寄付者にとって最も大きな懸念事項の一つです。
公益法人の場合、日常業務は事務局が行いますが、事務局が独断で使途を決定することはありません。事務局の活動は理事会によって監督されます。
理事会は年4回以上の開催が義務付けられており、日常的な活動内容を確認できます。また、理事会は監事(多くの場合、税理士や公認会計士などの専門家)によって、帳簿や議事録などを通じて厳しく監視されます。
さらに、公益法人の最終意思決定機関である総会(または評議員会)では、決算の承認、理事・監事の選任・解任などが行われます。総会で承認された決算書や事業報告書は行政庁に報告する義務があり、行政庁は報告書に基づいてチェックを行い、必要に応じて詳細な問い合わせを行います。
行政庁は3~5年に一度、公益法人事務所で立ち入り検査を行い、領収書や理事会議事録などの原本を確認します。
公益法人は、決算書、議事録、事業報告、役員名簿などの情報を公開する義務があります。これらの情報は、請求があれば開示しなければなりません。
これらのチェック体制を怠ると、行政からの指導が行われ、改善が見られない場合は公益法人の認定が取り消されることもあります。つまり、継続して活動している公益法人は、これらの厳しいルールを遵守していると言えます。
不安を軽減するための工夫
制度的な安心感を補完する要素として、一部の法人では寄付者との間で契約書を取り交わすことがあります。
- 「遺言書の内容が確実に実行されるのか」という不安を和らげるには、寄付契約書の作成が効果的です。契約書の形式は、協定書、同意書、申込書など多岐にわたりますが、いずれも寄付者と法人の間で合意内容を確認することを目的としています。
- 契約書を作成する利点は、寄付金の用途が明確になる点にあります。契約書には通常、寄付の目的や使途が具体的に記載されているため、担当者が交代した場合でも契約書に基づいて適切に対応できます。
- また、契約書の内容と異なる使途を試みた場合、監事によるチェックが行われる可能性が高く、理事会の承認を得ることは困難です。これは、理事会の信頼性や運営体制に関わる問題に発展する可能性があるためです。
- このように、遺贈寄付は多くの人々の目を通じて管理され、社会的監視のもとで運営されています。そのため、「寄付金が意図した通りに使われないのではないか」という懸念は、制度面と運用面の双方から軽減されます。
【まとめ】
遺贈寄付は、寄付者の想いを未来に繋げる手段の一つです。本稿が、寄付者の不安を解消し、安心して遺贈寄付に取り組むための一助となれば幸いです。