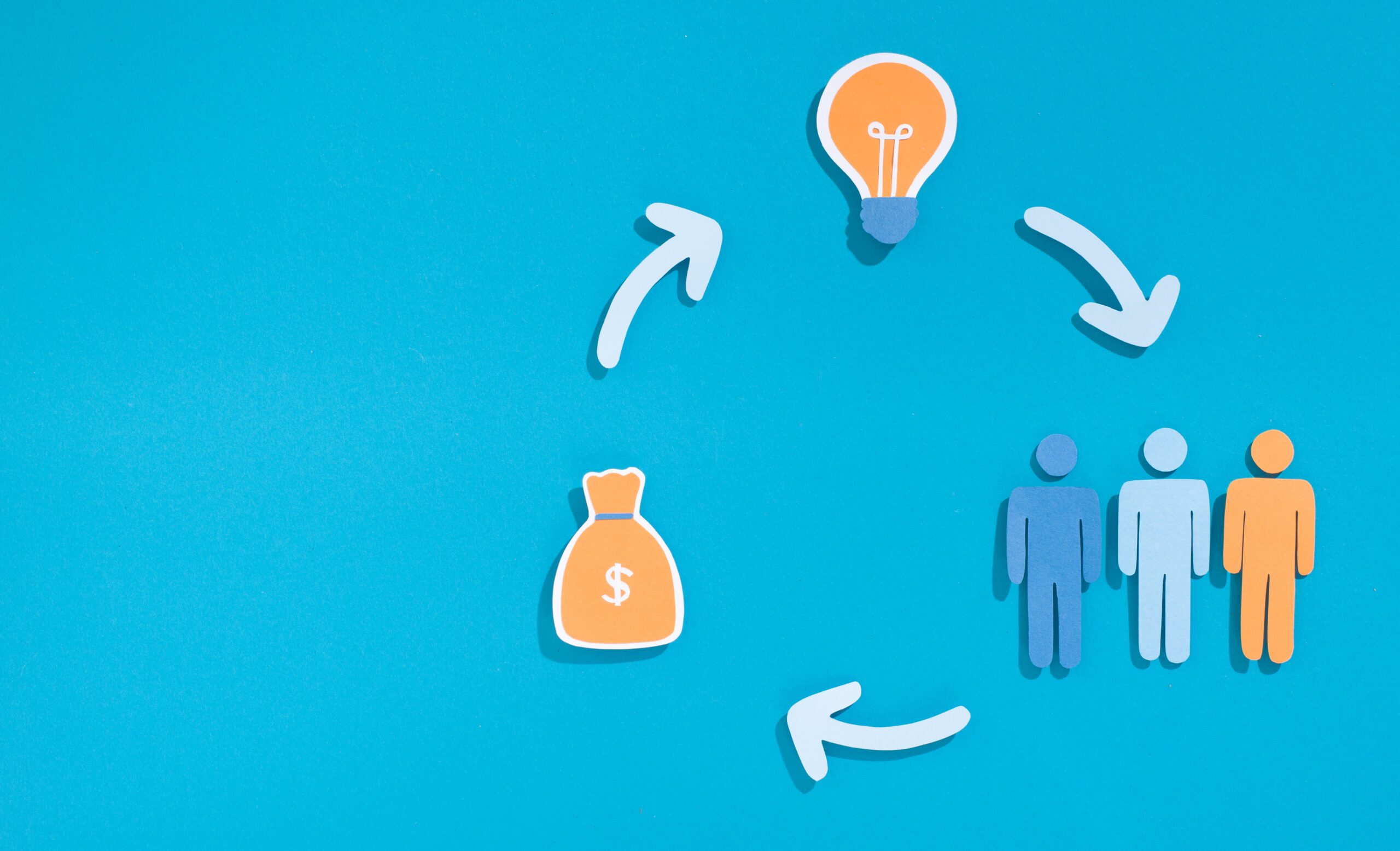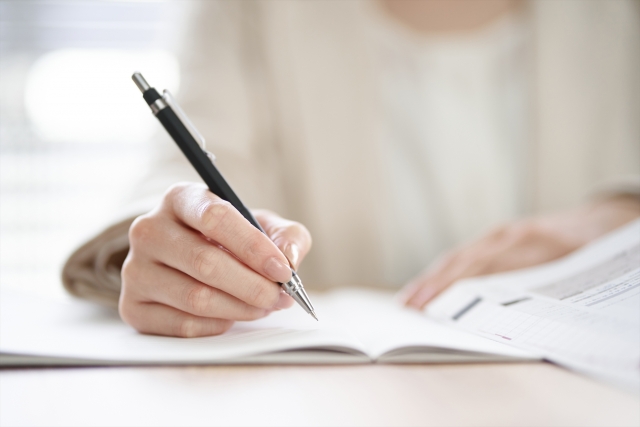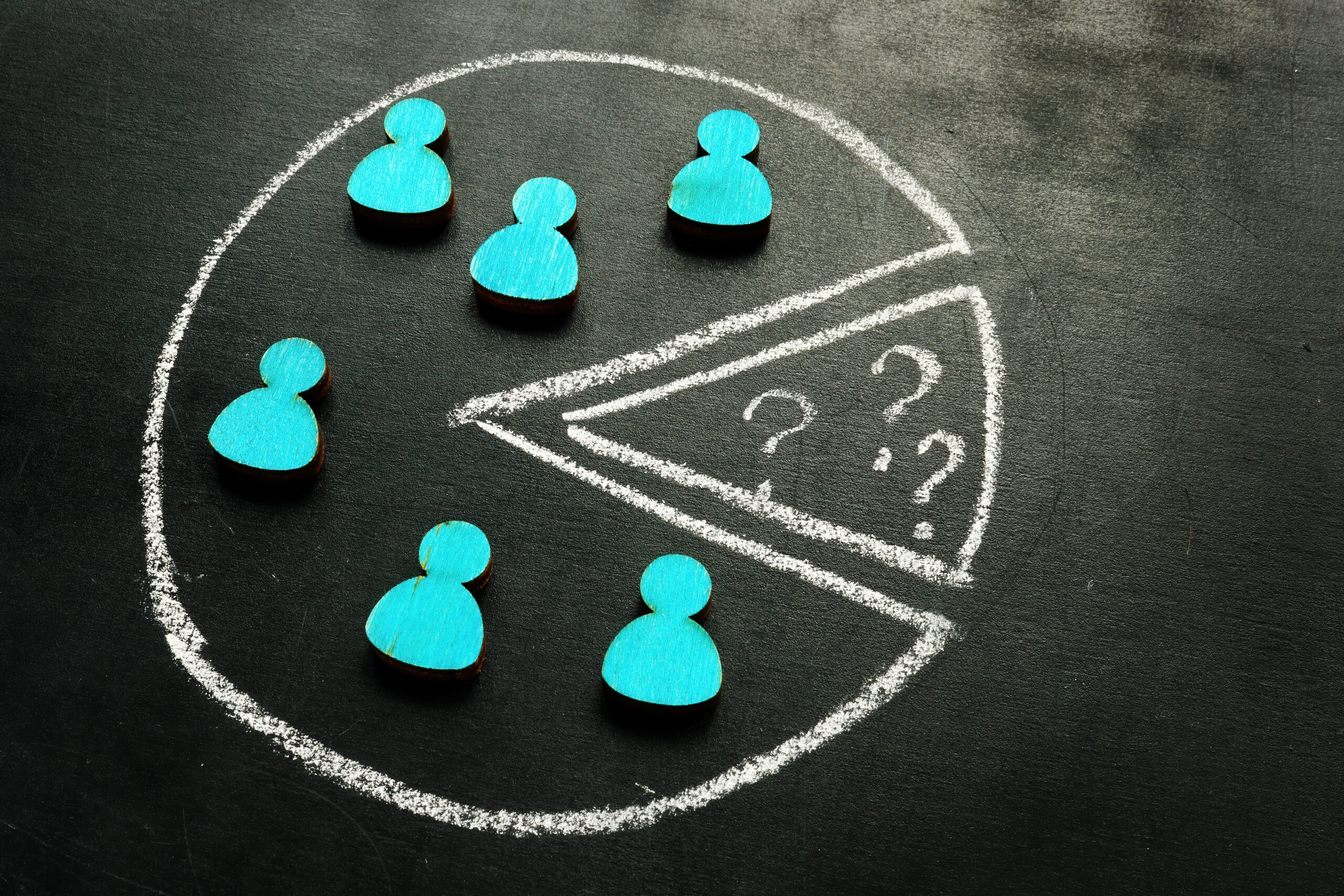結論からいえば、遺贈寄付では必ずしも特定の団体を決めておく必要はありません。代わりに、資金を適切に配分できるパートナー、つまり基金を選定することで、寄付者様の意思を反映した寄付が可能な場合もあります。運用の詳細と実例を併せて解説していきます。
一般に遺言書には特定の団体名を記載しないと寄付が執行されないことがあります。そのため、弁護士や信託銀行などは、遺言作成時に寄付先を決めるよう助言します。 しかし、遺言書作成時に寄付先を決められないケースもあります。遺言作成時に寄付先の団体を知らない、または存在しない場合もあるからです。また作成と執行に時間差が生じるという遺言の特徴から、未来の社会課題が変化し、寄付の用途が合わなくなる可能性もあります。遺言書を早く書く必要がある一方、寄付先を吟味したという希望もあるでしょう。
基金に託す
解決策の新しい考え方として、基金を作るという方法があります。
手順は以下の通りです。
・寄付を特定の団体ではなく、目的ごとにまとめます。(資金を目的のため使えるように)基金化することを遺言に明文化します。
・遺言執行時に基金を託した団体が適切な寄付先を選定します。
・さらに託した団体が公募を通じて新しい活動を支援するケースも期待できます。
基金のメリットは(1)寄付先を決めていなくとも遺言書を作成できることです。このため、遺言の作成を円滑に進められます。遺言の要件を満たすので、(2)目的をもった基金があれば、団体が存在しなくても寄付が可能です。必要に応じて遺言の趣旨に沿った新しい団体や事業体を立ち上げることができます。遺言の趣旨をより反映することができるのです。さらに(3)社会の変化に対応できます。時代が変化しても、遺言の趣旨により近い形で資金を提供可能です。
猫の保護活動への遺贈寄付
猫の保護活動への遺贈寄付の具体例を紹介します。
ある60代男性が、自身の資産を猫のために活用したいと考え、遺贈寄付を希望しました。彼は生前、猫を飼いたいと思っていましたが、一人暮らしで病気を抱えていたため実現しませんでした。しかし、最期が近づいた際、自らの財産を猫のために役立てたいと考え、寄付を申し出ました。
この男性の寄付を受けるにあたり、適切な寄付先の選定は容易ではありませんでした。猫の保護活動を行う団体は多数存在しますが、それぞれの規模や活動方針が異なり、適切な寄付先を選定するのが難しかったのです。また、既存の団体の多くは年間予算が10万円から100万円程度と限られており、400万円という寄付金を単独の団体に渡すのは適切ではないと判断しました。
また、猫の保護活動をしている団体からは「対症療法的な側面が強く、長期的な解決策が求めらる」という意見もありました。猫の問題の根底には、人間の福祉的な課題が関係しており、高齢者がペットを飼う際の支援が必要であることも明らかになりました。たとえば、高齢者がペットを飼えなくなった際の対応や、障害や病気を持つ人がペットを飼うことで生じるトラブルへの対処などが課題として挙げられました。
このような背景を踏まえ、寄付金の活用方法として、猫の専門家と福祉の専門家が連携するプロジェクトを立ち上げることになりました。動物保護の専門家は猫の世話や手術に精通していますが、高齢者や障害者とのコミュニケーションには特別な訓練を受けていません。一方で、福祉の専門家は人間の支援には長けているものの、猫の世話に関する知識は持っていません。そこで、両者が連携することで、より効果的な支援が可能になると考えられました。
さらに、寄付金の適切な配分が課題となりました。基金として分配することで、複数の団体に助成し、継続的な支援を行う仕組みを作ることが決まりました。これにより、単発的な支援ではなく、長期的な視点で猫と人間の福祉を向上させることが可能になります。
資金配分の具体策として、以下の3点が挙げられます。
(1)高齢者が適切にペットを飼うための支援プログラムの立ち上げ
(2)猫の保護活動を行う非営利団体への助成
(3)猫の虐待防止を目的とした活動への資金提供
高齢者がペットを飼うことについては賛否がありますが、適切な環境と支援があれば、高齢者の生活の質を向上させる効果が期待できます。そのため、ペットを飼うこと自体を否定するのではなく、適切な飼育方法を確立することが重要とされました。
さらに、基金の管理には信託銀行や公益財団法人の協力が必要となります。特に、公益信託は大規模な寄付向けの仕組みであり、ケースバイケースでの活用が求められます。そのため、資金の受け皿としてどの組織が最適かを慎重に検討することが重要になります。
今回の事例を通じて、単に動物保護への資金提供にとどまらず、福祉的な視点を取り入れた包括的なアプローチが必要であることが明確になりました。基金を作ることで、寄付者の意志を尊重しながら、社会全体にとって有益な形で寄付金を活用することが可能です。